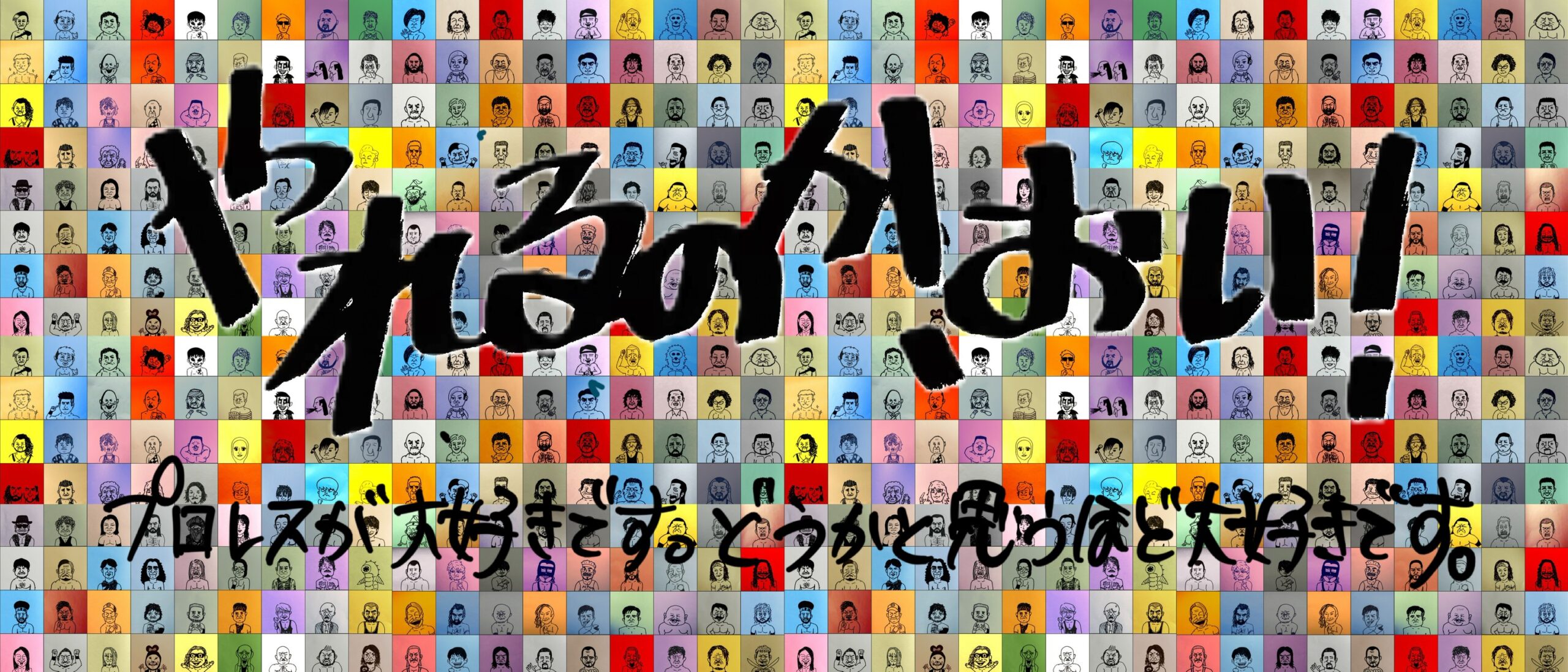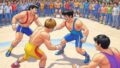新日本プロレス「G1 CLIMAX 35」は、KONOSUKE TAKESHITA選手の初優勝で幕を閉じました。
そして、最終戦ではちょっとしたサプライズが起こりました。第2試合終了後にヤングライオンだった中島佑斗選手とオスカー・ロイベ選手の「ヤングブラッド」が1年8か月の海外武者修行を終えて、Yuto-IceとOSKARの「Knock Out Brothers」として帰還してきたのです。
外国人選手のコンビは多々ありましたが、所属のヘビー級タッグとなると「NO LIMIT」以来でしょうか。これは活躍に期待したくなります!
が、新日本に限らず、日本ではタッグに特化した日本人コンビってなかなか誕生しませんよね。
日本の選手で現在タッグチームで活動しているコンビの一番手は、全日本の斉藤ブラザーズ。タッグチームとして大きく飛躍しました。が、他団体は…もう出てこないのです。
これは、なぜでしょうか。
今回は、日本ではなぜタッグマッチが主流にならないのか、タッグチームが定着するためにどうすれば良いか、というお話です。

タッグチームが定着しない理由
日本のプロレスにおいて、タッグマッチは興行の華として存在しますが、シングルマッチに比べると主流になりにくく、何より要になるべきタッグチームが長続きしないのが現実です。
その理由は何なのか、を考えてみました。
まず、歴史的に日本のプロレスは個人闘争としての価値を重視してきました。
過去の名勝負で思い出されるのはほぼシングルマッチ。各団体のリーグ戦やタイトルもすべてシングルのものが最高峰と言われ、そこにスポットライトが当たります。
その場合、タッグマッチはシングルマッチへの繋ぎ、前哨戦としての役割になってしまいます。
アクシデントが起きた際も影響があります。
特定のタッグで活動し続けている最中に、どちらかが予想外の怪我などで欠場になると当然コンビ揃っての計画が消えてしまいます。その場合は他の選手との急造タッグで乗り切らないといけませんし、もしこれが評価を得た場合はこれまでのタッグを継続せず解消、とアクシデントの影響も定着が難しい要因です。

タッグはシングルより価値が低いのか
また、「タッグはシングルよりも価値が低い」という根拠のない風評被害も待ち構えているので、選手にとってはタッグだけの評価で支持を得るのが難しいのが現状です。
その時点でシングルの王座に挑戦できるようなトップ選手はシングル戦線が主戦場となるため、なおさらタッグで活躍することができなくなります。
ファンの心理にも「選手の真価はシングルでこそ」というイメージが多いです。
これらの要因を覆すのはかなり困難かもしれません。
かつてはそのイメージを覆そうとファンの意識改革に乗り出した選手や団体もありました。
そのシリーズで一番動員が見込めるビッグマッチのメインにあえてタッグマッチを組んだり、主力選手をタッグ戦線に加入させたり。それが成功し定着すれば、タッグマッチの商品価値が高まり、新たな展開もプロレスの幅も広がります。
ひとつの試合で多くの絡みが見られるお得さ。派手な連携技と数珠つなぎや連鎖反応のような攻防。選手が入り乱れたまま試合が進む疾走感。シングルマッチにはないタッグマッチならではの魅力も増えました。
ですが、現代のプロレスの性質だと「シングル>タッグ」の図式は変わらないでしょう。

形式よりも選手に価値がある
考えれば考えるほど「プロレスは個人闘争」という基本理念を崩すのは相当困難なようです。
であれば、考える軸を変えてみるしかありません。
タッグマッチという試合形式よりも、タッグマッチでの試合を見たくなる選手が現れたら良いのです。
価値はルールではなく選手にあるものですからね。
そして、きっとそこに価値を求める選手は出てくるでしょう。タッグマッチは他の格闘技にはない、プロレスならではの風景を最大限活かせる場所だと思うので。
今回のまとめ
タッグマッチがシングルマッチより上になるのは難しい
だからこそ「この選手のタッグマッチが見たい」と思わせる選手が出てきてほしい

広大な畑で育てる、タッグの実
開拓されては荒廃の繰り返しを続けるタッグという広大な畑。
決して未開の地ではないが、ここで大きな実がなれば千載一遇のチャンス。
斉藤ブラザーズが欠場中の今、Knock Out Brothersがその畑を耕そうとしています。
さあ、どんな実がなるでしょうか。
実りの秋は、すぐそこです。
では、またここで。