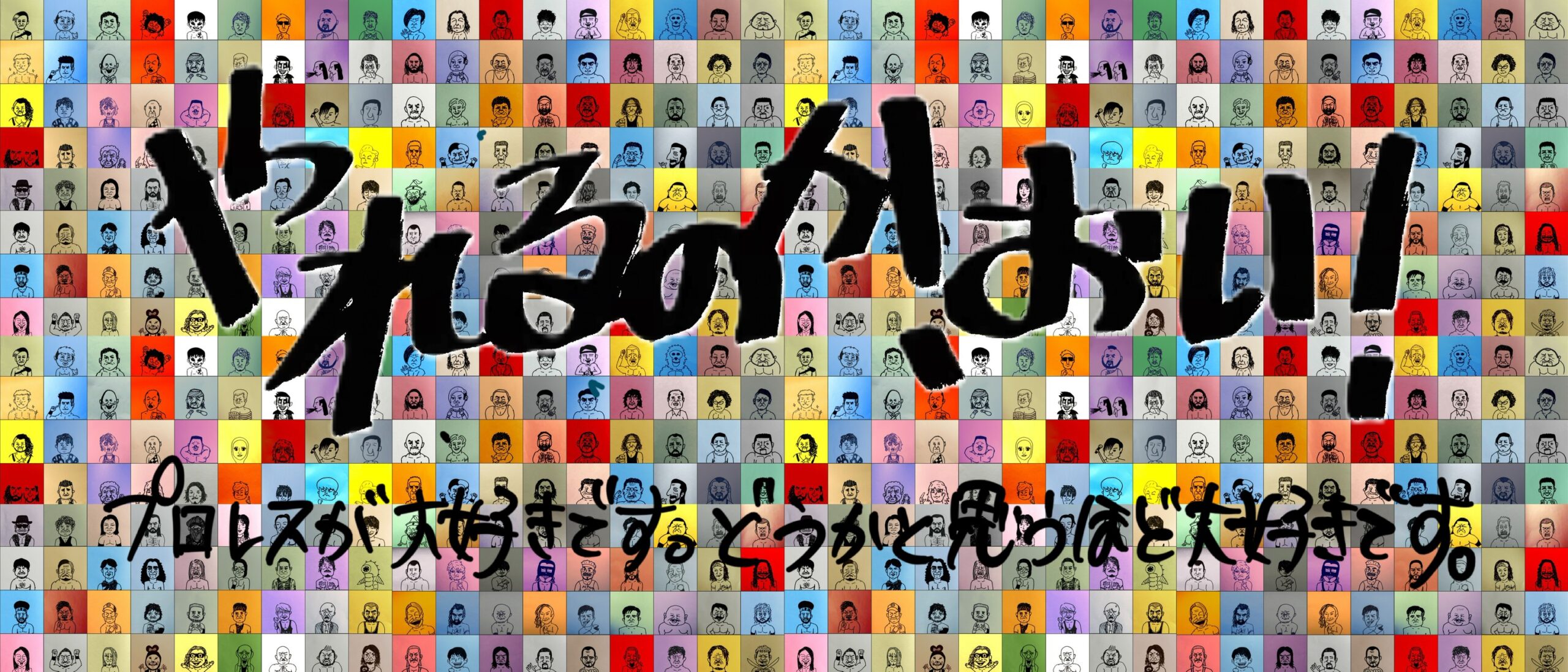出世魚ではないですが、初心者がファンへと成長し、さらに熱心になるとマニアに変化します。
そして、年数や経験を重ねた愛情の先にあるのは、その距離感をキープしたままの「マニア」、好きを拗らせた何でも許容してしまう「信者」、思い通りにならないと攻撃してくる「アンチ」、感情よりも脳が先に動く俯瞰的な目を養った「審査員」、以上の4種に分岐されるのではないでしょうか。

プロレスファンには審査員が多い?
プロレスファンの場合、ほかのジャンルに比べて「審査員」になる人が多い気がします。
野球やサッカーなどのプロスポーツでも選手に対しなぜか上から目線で物を言ってくる人はいます。スポーツだけじゃなく、お笑いだったり、麻雀だったり、アニメ作品だったり、アイドルだったり、自分が評論家なりディレクターにでもなったつもりで正論ぶった意見を言う人はたくさんいます。
ファンは「消費者」。なのでその楽しみ方や味わい方は千差万別。目の前の試合や出来事を楽しむ延長として評論や考察というものがあるのでしょう。
プロレスファンの場合、試合以外でも、有望な選手が支持されない理由、団体側の策略の是非、アクシデントが起きたときの原因解明と責任、憶測でしかない選手や団体間の裏話、など、詳しくなればなるほどプロレスというものを審査員視線で評価しがちです。それは愛情があればこそ語れるものなので良いことでもあります。不平不満や文句だけを並べるような害しか生まないアンチではありませんし。
では、なぜプロレスファンは「審査員化」してしまうのでしょう。今回はこれを考える、というお話です。

なぜ「審査員化」するのか
ほかのジャンルもそうですが、特にプロレスファンが「審査員化」する理由、「純粋に楽しむ」ことから離れてしまう現象は、心理や現代のコミュニティが影響を与えていると考えます。
特異的な構造
プロレスは、ストーリー展開と試合パフォーマンスが融合した独特のエンターテインメントです。ファンは勝敗だけでなく、試合の内容、組み立て、技術、的確さ、アピール、観客の反応、といったプラスアルファの要素にも注目します。このプロレスにしかない特異的な構造が、ファンを「見る側」から「評価する側」にシフトさせる土壌を作っているのかもしれません。
プロレスは「何が起こるか」と同時に「それをどう表現するか」が重要なので、自然と「審査員目線」が育まれやすいのでしょう。
ファンのコミュニティ意識
また、ファンによる「知識の誇示」や「存在証明」も関係しています。
プロレスに限らず、野球、サッカー、アニメ、お笑いなどの熱心なファンは、自分の愛するジャンルに対する深い理解や情熱を共有して仲間との絆を深めたり自己表現を行います。その過程で「自分は単なる観客ではなく、このジャンルを深く理解している」と見せつけるアピールのために、純粋な楽しいや面白いという感想を超えて「考察」や「批判」に走るファンが増えるのだと思います。
現代の情報発信環境
そして何より、現代の情報発信社会の影響が強いでしょう。
SNSで意見を発信する文化が広まり、ファン同士だけでなく選手や団体スタッフが簡単にリアルタイムで感想や評価を目にすることができるようになったことで、あえてそれを利用する人が増えました。
プロレスファンの「審査員化」は、そうした意見交換の中で「自分の見解がどれだけ鋭いか」を試したい、認められたい、という欲求もあるのではないでしょうか。
判断を下す心理的快感
最後に、これはどのジャンルでも共通することですが、人間には「判断を下す」ことに快感を覚える心理的な側面があるそうで、その影響が大きいのかもしれません。
プロレスの試合を見て「この技のタイミングが完璧だった」「あのストーリーは無理がある」と判断を下すことは、単に受け身で楽しむよりも積極的な関与感を与えてくれます。
好きだから、という本質
以上の項目が絡み合った結果が、プロレスファンの審査員化の要因かと思われます。
ですが、それこそが「ファン心理」という存在の本質なのかもしれません。楽しめるから評価ができる、でもあり、評価できるから楽しめる、という表裏一体のバランスだと言えます。
ただ、主体はあくまで選手や団体。リングの上です。
好きなものに夢中になれること、好きなものを見られること、好きなものを批評できる環境には感謝したいですね。
今回のまとめ。
ファンは審査員ではない
ファンは単なる消費者でもない
ファンはジャンルを成長させる糧である

と、プロレスファンの審査員化を考察してみる、というファンの私も審査員化してるのですが。
無限ループですね。プロレスの魅力と同じですね。
では、またここで。