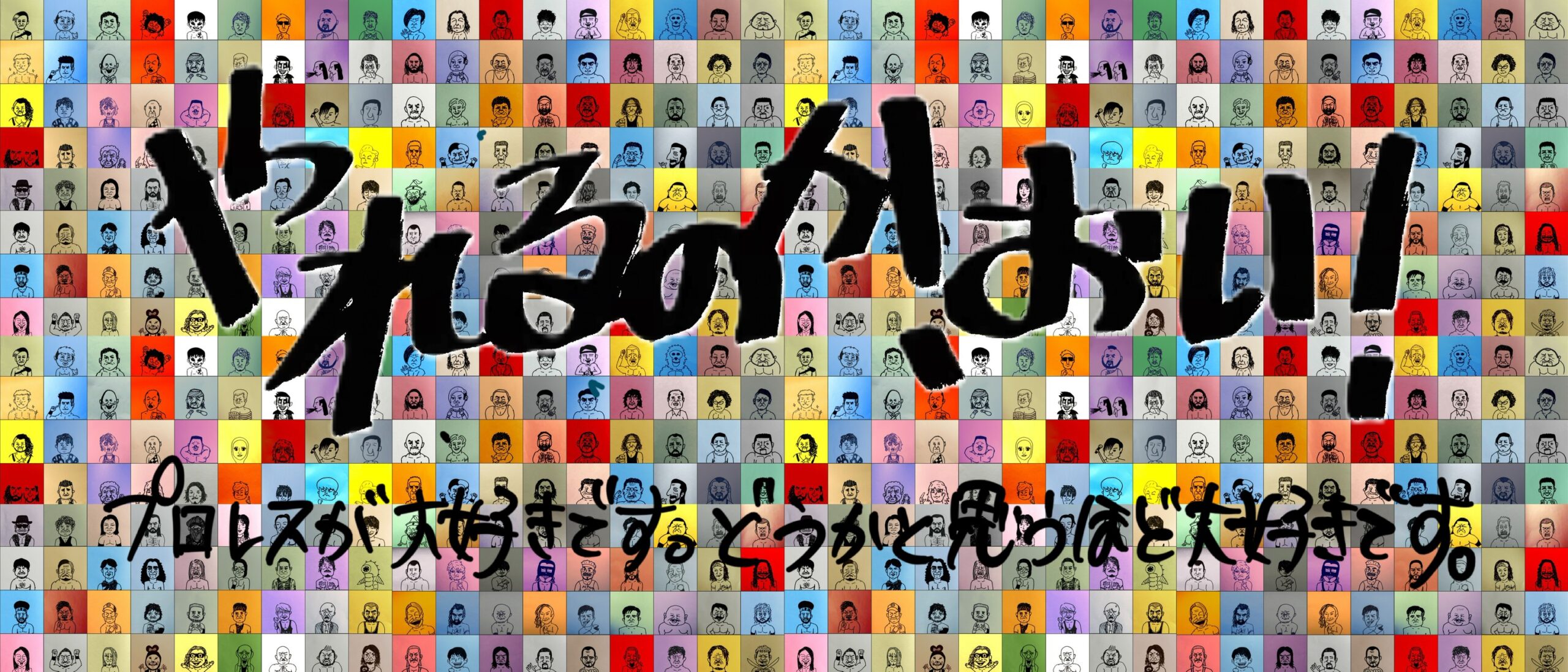では、さっそく前回のつづきです。プロレスと感情移入について。
今回は「感情移入させる方法」と「感情移入できる選手」についてのお話から。

感情移入のカギは闘争心
詳しくない人、はじめて観戦をする人にプロレスの魅力を伝えるならば、やはり「超人的な技とそれを受ける肉体」は大事です。ただ、それだけではアクション映画やサーカスなどの鑑賞後と同じ「凄い!」という感情まで。その先の「また見たい」「情報を追いかけたい」になるには、初見でどこまで選手が感情移入させられるかがカギになります。
はじめてでも心を動かせる、一番わかりやすく、大前提としてプロレスラーに必須な感情表現。それは相手に勝つ気持ち。負けない、負けたくないという不屈の精神。プロレス的ワードでいうと「闘争心」を見せることです。逆を言えばプロレスにおいて相手に勝つという気持ちがなければジャンルとして成立しない、とも言っていいでしょう。闘争心が観客に伝われば、観戦歴の長短関係なく感情移入ができます。

選手タイプ別の感情移入
ベテランのプロレスラーほど声援や後押しが大きくなるのは、これまでのキャリアで感情移入の要素をたくさん積み重ねてきたからです。トップ戦線で活躍していた頃、怪我による欠場、過去の対戦相手、そして現在。あらゆる「歴史」の視点から感情移入できるのがベテラン選手の強みのひとつです。初見の観客にも「この選手はこんな高齢なのにこんなに体も魂も削ってプロレスしている」という姿勢が見えればそれも感情移入の入口のひとつ。ベテラン選手は体が思うように動かなくても、むしろそれすら感情移入につながります。
じゃあ若手選手は感情移入できないのか。というものではありません。デビュー間もない若手選手には「がむしゃら」という闘争心があります。新日本でいうヤングライオンたちが技よりも全力で声と気合いを出すのは、短いキャリアでも相手に喰らいつく闘争心で感情移入させるため、という側面もあるかと思います。
表情が見えないマスクマンは、全身の「アクション」で観客に気持ちを伝え、感情移入を呼び込みます。表情がないから劣るのかと言えばむしろ逆で、それ以外の方法で伝えることで、観客はマスクの下の表情がどうなっているのかをも想像し、感情移入が増します。ただ、そこまでたどり着くのは並大抵のことではないですが。
外国人選手も同様、言語も文化も異なるため言葉などで伝えることは困難ですが、あらゆる手段で観客を感情移入させれば、日本人選手以上の感動を呼ぶことができます。

意外性と緩急とTPO
このように、プロレスラーは全員、さまざまな観戦歴の観客を感情移入させることが可能です。感情移入させられないことはただの言い訳でしかない、とも思います。
ですが、闘争心を全力で見せれば誰でも名レスラーになれるのかといえばそうではありません。感情移入させるために大事なのは、その表現を出すタイミングや方法です。
闘争心の表現方法も様々です。雄叫び。表情。アクション。技。言葉。ただ、これらをひとつの試合でたくさん出せばいい、ということではなく、試合のシーンにおいて何が適切な自己表現なのかをしっかり見極め、それが観客にどう伝えられるか、意外性と緩急とTPOが必要なのです。
また、プロレスファンは感情移入の押し売り行為に敏感で、それが見えると一気に醒めしてしまう人種です。闘争心の中に「負けたくないです!がんばってます!応援してください!」が出てしまう選手には、感情が動かされないどころか拒絶反応まで出てしまうことも。プロレスファンって目利きや嗅覚が鋭くて、良くも悪くも選手に媚びないのです。早くにトップ戦線へ加わる若い選手が表現を誤りがちですが、そこをクリアしてしまえば体格や運動神経以上の武器になるでしょう。

感情移入は生きざまあってこそ
プロレスという競技は肉体を使った自己表現。観客に感情移入させるために、いかに自分を客観的に見られるか。そして、それを踏まえて自分の闘争心をどのような方法で表現するか。選手それぞれの「生きざま」をぶつける闘いです。
そんな同調するはずのない選手同士の生きざまが交錯して爆発したとき、最高の試合、最高の歓声、最高の空間が生まれるのだと思います。
クオリティの高い試合、繰り出される多くの技、ビジュアルやフィジカルだけでなく、選手が見せてくれる生き方で感情移入し気持ちが揺れ動く感覚こそ、プロレス観戦における特別な瞬間です。もちろん、気持ちの揺れの大きさや感動ゾーンの広さはファンの人によって異なります。ですが、どうせ見るならその部分を大きくして、特別な瞬間をより多く感じてみませんか?

今回のまとめ。
プロレスは感情移入することで
ファンだけの特別な瞬間が味わえる
私の感情移入?それはもう、気持ちの揺れ方は首が座ってないくらいグラグラですし、感動ゾーンの大きさは小学生の遠投でもボールが全部命中するくらいデカデカです。
では、またここで。